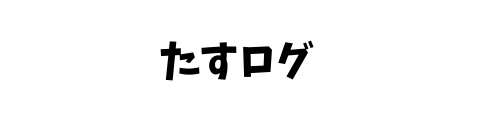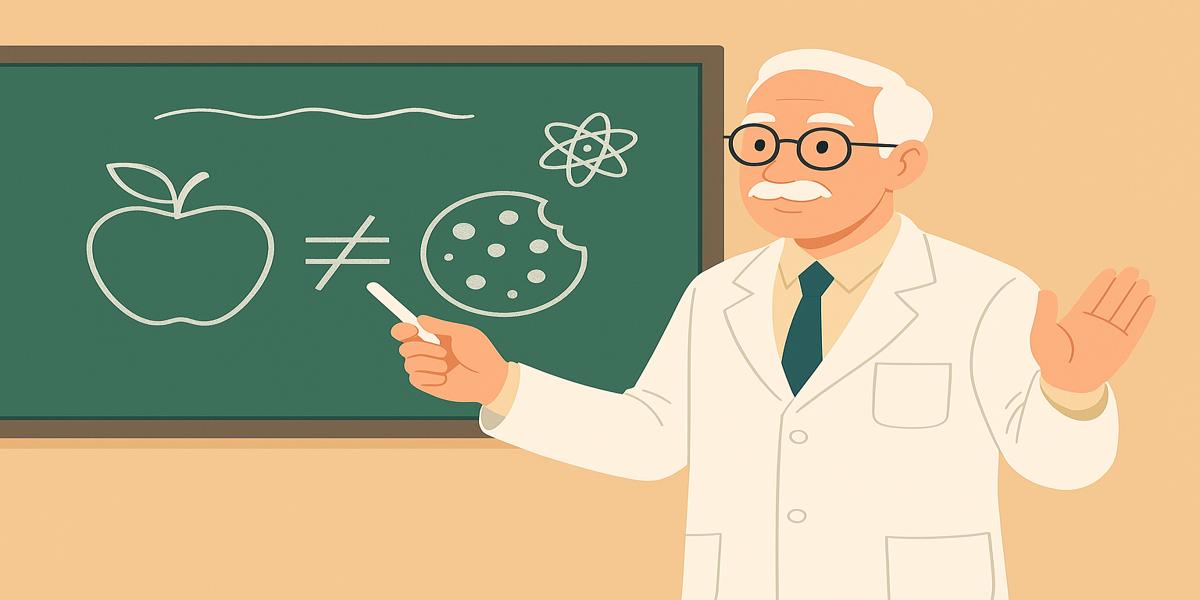「ダイエット中なのに、つい間食してしまう…」
これは多くの社会人が抱えるお悩みではないでしょうか。
仕事の合間についお菓子に手が伸びてしまったり、
ストレス発散に甘いものを食べてしまったりする経験、ありますよね。
実は間食自体はとても一般的な習慣で、あるグローバル調査では
91%もの人が毎日何らかの間食をしていると報告されています。
特に忙しい現代人にとってお菓子やスナックは手軽な「エネルギー補給&癒し」となっており、
81%の人が日々のストレス解消のために間食するとも言われます。
間食は決して珍しいことでなく、あなただけが意志が弱いわけではありません。
しかし、ダイエット中であれば「できれば間食を減らしたい」
「不健康なおやつをやめたい」と思いますよね。
ではなぜ人は間食してしまうのか? そしてどうすれば科学的に間食を減らせるのか?
本記事ではその原因と対策を解説します。
意志力だけに頼らず、環境や習慣を工夫することで「間食しない仕組み」を作り、
無理なくおやつ癖を手放す方法を一緒に見ていきましょう。
なぜ人は間食してしまうのか?(心理・ホルモン・習慣)
まず、間食をやめる方法を考える前に、「なぜつい間食してしまうのか」を理解しましょう。
理由を知れば対策のヒントも見えてきます。
人が間食してしまう主な要因には、心理的なストレスや習慣、体のホルモンや血糖の変化
、環境要因などが絡んでいます。
それぞれ科学的根拠を交えながら解説します。
ストレスで食欲が増すメカニズム
仕事や人間関係のストレスがあると、私たちの体は「コルチゾール」というホルモンを分泌します。
このコルチゾールは食欲を高め、さらに「何か食べたい!」という
動機づけも強めてしまうことが分かっています。
短期的な強いストレス(例えば急な締め切り対応など)では
逆に食欲が一時的に落ちることもありますが、ストレスが慢性的に続く場合、
常にコルチゾールが高い状態が続き食欲が増進してしまうのです。
さらに厄介なことに、ストレス下において人は
高脂肪・高糖質の「いわゆるジャンクフード」を求めやすくなる傾向があります。
研究によれば、ストレス時には甘くて脂肪たっぷりの食べ物が
欲しくなることが確認されています。
これは、糖分や脂肪分の多い食べ物が脳のストレス反応を和らげる効果を持つためで、
実際にこうした「ご褒美お菓子」は一時的にストレスを減らす
“自己治療”的な役割を果たすことが分かっています。
そのため、イライラしたときについ甘いものに手が伸びるのは、
生理的にも説明がつく現象なのです。
社会人は仕事上のプレッシャーも多いため、
ストレス→ホルモン変化→食欲増進というルートで間食が増えてしまうことは珍しくありません。
習慣と環境が招く“つい食べ”
人はしばしば習慣的・無意識的に間食しています。
実は私たちの行動の約半分は毎日同じ場所・同じ時間帯に繰り返される習慣的行動だと言われます。
例えば「午後3時になると自販機で甘いカフェオレを買ってしまう」
「仕事終わりにコンビニに寄ってお菓子を買う」など、環境や時間がトリガー(誘因)となって、
本人の意識や意思とは無関係に間食行動が起きていることが多いのです。
デューク大学のウエンディ・ウッド教授の研究によれば、
「習慣が定着すると、いちいち意思決定をしなくても環境のキュー(合図)に反応して
自動的に行動が出てしまう」とのこと。
つまり、「今日はおやつ控えよう」と頭で思っていても、
いつもの時間・いつもの場所にいると手が勝手に動いてしまうのです。
環境要因の威力を示す有名な実験があります。
オフィスの机に置いたキャンディの量を変えてみた研究です。
コーネル大学の研究チームは、職場のデスクに
透明または不透明な容器に入れたチョコレートを置いた場合と、
少し離れた棚に置いた場合で、1日の消費量がどう変わるかを調べました。
その結果は驚くべきもので、お菓子が「見える・手に取れる」状態だと
圧倒的に多く食べてしまうことがわかったのです。
具体的な数字は以下の通りです。
表1:職場のデスクに置いたキャンディの視認性・距離と1日あたりの平均消費個数。
| 配置環境条件 | 1日の平均摂取量 (Hershey’s Kisses 個数) |
|---|---|
| デスク上・透明な容器に入れる | 約7.7個 |
| デスク上・不透明な容器に入れる | 約4.6個 |
| デスクから約2m離れた場所・透明容器 | 約5.6個 |
| デスクから約2m離れた場所・不透明容器 | 約3.1個 |
ご覧の通り、お菓子が視界に入らず手の届かない場所にあるだけで、
摂取量は半分以下に激減しています。
机の上に透明な瓶で置かれていた場合と、
少し離れた場所に不透明な容器で置かれていた場合では1日あたり4個以上も差が出ました。
この実験では参加者は自分が食べた量を過小評価する傾向も見られ、
人は「近くにあるとつい食べちゃうけど、遠いとそんなに食べてないはず」
と錯覚することも示唆されています。
つまり、環境が私たちの間食行動を大きく左右しているのです。
オフィスにお菓子の差し入れがあれば手が伸びますし、
家のリビングにお菓子ボウルがあればテレビを見ながらつまんでしまうでしょう。
習慣と環境によって「つい間食」が起きる仕組みがある以上、
これに対策を打たないと意志だけで抗うのはなかなか難しいわけです。
お腹が減る生理的な理由(ホルモン・血糖)
もちろん、空腹感そのものも間食の大きな要因です。
本来、間食はお腹が空いたときにエネルギーを補給する役割ですから、
なぜそんなにお腹が減るのかという生理的側面も理解しておきましょう。
ポイントはホルモンと血糖(血液中のブドウ糖)の動きです。
まず、空腹感を生み出すホルモンとして「グレリン」があります。
グレリンは胃から分泌されるホルモンで、
血中グレリン濃度が上がると脳に「お腹が空いた、何か食べよう!」という信号が伝わります。
規則正しい食事習慣のある人では、
食事の時間が近づくとグレリンが増えて空腹を感じるというリズムができます。
一方、満腹を伝えるホルモンとして「レプチン」があります。
レプチンは脂肪細胞から分泌されるホルモンで、
体にエネルギーが十分蓄えられていると脳に満腹信号を送ります。
グレリンが上がると食欲増進、レプチンが上がると食欲抑制という関係です。
では、ダイエット中で食事量を減らしたり、不規則な生活を送ったりするとどうなるでしょうか?
いくつか注意すべき点があります。
まず、睡眠不足は空腹ホルモンに悪影響を与えます。
スタンフォード大学の研究は、慢性的に睡眠が足りない人はホルモンバランスが崩れ、
食欲を刺激するグレリンが増えて、満腹を伝えるレプチンが減少することを明らかにしました。
実際、5時間睡眠の人は8時間睡眠の人に比べて血中グレリンが約15%高く、
レプチンは15%低いというデータが報告されています。
その結果、睡眠不足の人ほど空腹を感じやすく太りやすい傾向が見られています。
睡眠が短い社会人ほど午後に「なんだかお腹が減って集中力が切れる…」
となりがちなのは、こうしたホルモン変化が一因かもしれません。
次に血糖値の変動も間食欲に影響します。
例えばお昼に白米や菓子パンなど高炭水化物・高GI(グリセミック指数)の食事を摂ると、
食後しばらくして血糖が急降下する「血糖値スパイク後の谷間」が起こりやすくなります。
すると脳は血糖の低下を「エネルギー不足」と捉え、強い空腹感や甘いもの欲求を引き起こします。
最近の研究でも、食後2〜3時間後の血糖値の急激な低下が、
その後の空腹感の強さや追加のエネルギー摂取量を増やす
明確な予測因子になることが示されています。
簡単に言えば、食事で血糖が乱高下すると、
その数時間後に余計にお腹が空いて間食に走りやすくなるのです。
さらに、食事内容の偏りも空腹感に影響します。
例えばタンパク質や食物繊維が不足し、糖質中心の食事ばかりだと満腹感の持続時間が短くなります。
タンパク質は三大栄養素の中でもっとも満腹ホルモンを刺激しやすく、
胃腸での消化もゆっくりなため腹持ちが良い栄養素です。
実際、高タンパク食は食欲を抑え、間食や総摂取カロリーを減らす効果が多数報告されています。
ある研究では、食事中のタンパク質比率を15%から30%に増やしただけで、
被験者たちは1日の摂取カロリーを平均441 kcalも自発的に減らしたとされています。
これはタンパク質によって食欲が自然と抑制され、
間食や過食が減ったためと考えられます。
このように、ストレスや習慣(心理面)とホルモン・血糖(生理面)の両方から、
私たちは間食しやすい状況に置かれています。
「つい間食」は意思の弱さではなく、人間として自然な反応とも言えます。
しかし裏を返せば、これらの原因にアプローチすれば間食を減らすことができるはずです。
次の章では、そのための具体的で科学的な方法を見ていきましょう。
間食をやめるための方法
間食の原因がわかったところで、いよいよ具体的な対策に移ります。
ただ「もうお菓子は食べない!」と気合で我慢するだけでは、
前述の通り限界があります。
そこで鍵になるのが環境づくりと行動習慣の工夫です。
最新の科学的知見に基づいたアプローチをいくつか紹介します。
環境を整える:見えない・手に届かない工夫
間食を減らす第一歩は、自分を誘惑するお菓子たちと距離を置くことです。
前述のキャンディ容器の実験が示すように、
目の前にお菓子があるかないかで食べてしまう量は大きく変わります。
そこで、職場でも家庭でも「見えない・すぐ取れない」環境を意識して作りましょう。
自分の周囲の環境を間食しにくいように整えることは、
意志力に頼らないスマートな戦略です。
特に一日の終盤、疲れて意志力が落ちているときでも、
環境が整っていれば間食を最小限にできます。
習慣を置き換える:意志ではなく仕組みで断つ
長年染み付いた間食の習慣そのものにもアプローチしましょう。
習慣は意志で押さえつけるより、
他の行動に置き換えて上書きする方が成功しやすいと言われます。
いくつか有効な方法を紹介します。
「○時になったら△△する」を決める
いつも間食してしまう時間帯(例えば午後3時)には、
代わりの行動をルーティン化してしまいましょう。
例えば「15時になったらハーブティーを淹れてホッと一息つく」
「軽くオフィスの外を散歩してリフレッシュする」など、
おやつ以外の楽しみを習慣にします。
ポイントは、いつもお菓子を食べていた時間・場所で
別の行動をあらかじめ計画しておくことです。
そうすれば「いつもならお菓子の時間だけど、代わりにお茶を飲もう」と
スムーズに置き換えられます。
これは「習慣の置換」と呼ばれるテクニックで、
悪い習慣を良い習慣に上書きする効果的な方法です。
「間が持たない」を他の方法で解消
仕事の区切りや休憩時間に「何か口に入れないと落ち着かない」場合、
その“間が持たない”感覚を別の手段で満たしましょう。
例えば、シュガーレスガムを噛む、白湯やコーヒーをゆっくり飲む、
深呼吸やストレッチをする等です。
特にガムを噛む行為は咀嚼欲を満たし、集中力も高めるのでおすすめです。
重要なのは、「手持ち無沙汰=お菓子」という結びつきを断ち切ること。
別の行動パターンを用意しておけば、そちらに意識を向けることで
自動的なお菓子探しを防げます。
意志力任せで習慣に逆らうのではなく、
習慣の方を自分に有利な形に作り変える発想が大事です。
習慣化した行動は、疲れているときでも自動的に続けられるというメリットがあります。
ですから、「間食しない習慣」さえ作ってしまえば勝ちなのです。
ストレス・感情に対処する
ストレス発散がお菓子に向かいやすい人は、お菓子以外のストレス対処法を用意しましょう。
例えば、仕事で疲れたら5分だけ席を離れてストレッチをする、
深呼吸をして瞑想のように心を落ち着ける、好きな音楽を1曲聴く、
同僚や友人と少しおしゃべりする…など何でも構いません。
「疲れた→甘いもの」のパターンを「疲れた→○○してリフレッシュ」に書き換えるイメージです。
ハーバード大学の健康ガイドでも、
ストレスを感じたら冷蔵庫を開ける前に他のリラクゼーション法を試すことを勧めています。
瞑想や軽い運動(ヨガや散歩)はコルチゾールを減らす効果もあるので、
ストレス食いを防ぐ助けになります。
また、マインドフルネスを日常に取り入れるのも有効です。
マインドフルネスとは「いまこの瞬間の自分の状態に意識を向ける」ことで、
具体的には「本当に自分は空腹なのか?それとも退屈なだけか?」と
立ち止まって考える習慣をつけます。
間食したくなったらすぐ食べるのではなく、
まずコップ一杯の水を飲んで2〜3分待ってみるのも一つの方法です。
その間に「自分はなぜ今お菓子を食べたいのだろう?」と感じてみると、
「単に暇なだけかも」「イライラしているからだ」と気づくかもしれません。
自分の感情や体の状態に気づけば、
「じゃあお菓子じゃなくて○○しようかな」と別の選択肢を取れるようになります。
実際、短い瞑想の習慣は暴飲暴食を減らす効果が確認されており、
意識的に食欲と向き合うことで感情に流されにくくなるメリットがあります。
どうしてもお腹が減って集中できないときは、無理に我慢しすぎないことも大事です。
我慢しすぎて仕事の効率が落ちては本末転倒ですし、後でドカ食いしては意味がありません。
その場合は、ナッツ類やゆで卵、プレーンヨーグルト、プロテインバーなど
血糖値を急上昇させにくい間食を少量とりましょう。
ポイントは「間食するなら質の良いものを計画的に」です。
だらだらとビスケットや飴を舐め続けるのではなく、
「小腹が空いたからナッツを一握り食べよう」など内容と量を決めて摂るようにします。
実は間食自体は悪いことではなく、内容次第ではむしろ健康的に空腹をしのぐ手段になります。
重要なのはコントロールできない間食をしないことです。
そのためにも、以上のような環境・習慣・生活リズム・ストレス対策を組み合わせて、
「間食しなくても大丈夫な自分」を作っていきましょう。
最後に
間食をしてしまうのは意志の弱さだけではありません。
知らずのうちに皆さんが間食をしやすいような環境に身を置いてしまっているだけです。
間食をしてしまうなんて、なんて意思が弱いんだ。。。と思わずに
まずは身の回りを見回してみましょう!
近くにお菓子はないか、食事内容や生活リズムは規則正しいか
まずはできるところから直してみてはいかがでしょうか?
何事もいきなりガラッと変えることはできません。
コツコツ積み重ねるしかありませんので
昨日の自分より少し成長していれば十分です!
それが一か月、半年、一年続いていけばいつかは間食を辞められるはずです!
皆さんのダイエットが成功することをお祈りしています。